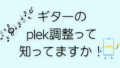前回ファーストアルバムについて書いてからずいぶんと時が流れてしまいました。その間、改めて彼らの足跡を辿るドキュメンタリー映画を観たり、ヘッドホンで音の層を分解するよう聴き返したりしていましたが、ようやくこの「茶色の爆弾」こと「Led Zeppelin Ⅱ」について書く準備が整った気がしています。
ファーストアルバムがペイジとボーナムによる鮮烈な「衝撃」だったとするなら、この『Led Zeppelin Ⅱ』は、バンドがある種「ポップ・アート的」に変貌を遂げた一枚ではないかと考えます。
そこで今回は、昨年観た映画でのペイジの言葉や、ふと思い当たったアート作家アンディ・ウォーホルとの共通点、そしてヘッドホン越しに見えてきた各メンバーの躍動について、考察してゆきます。
ペイジは音の編集者であり、音のアンディ・ウォーホル!?
セカンドアルバムを語るうえで外せないのは、なんといってもロック史を代表する名曲「Whole Lotta Love」。エレキギターの6弦と5弦、さらに実は4弦開放(D音)を混ぜることで、あの独特の唸るような倍音を生み出しているのですが、このシンプルかつ緻密なリフレインは、LED ZEPPELINというバンドの飛躍、また他にはない個性・表現方法を見せつけた彼らの伝説への招待状刻印。
「Whole Lotta Love」テレキャスターからレスポールへ
ペイジはファーストアルバムでは、フェンダー<テレキャスター>をメインに使っています。学生時代からの友人ジェフ・ベックから贈られたギター。これをメインに使用していたのですが、ハウリングの多さに悩んでいたところ、ギタリストのジョー・ウォルシュから勧められギブソン<レス・ポール・スタンダード>(通称#1)を手に入れ、セカンドアルバムではメインとして使っています。
テレキャスターのエッジの効いた鋭いサウンドからレス・ポールのパワーと色気の同居したサウンドへと進化。このメイン楽器の変化が重厚でメタリックな「Whole Lotta Love」のリフを生み出したと言っても過言ではないでしょう。あのリフについて、ドキュメンタリー映画のなかでプラントは「絶対にいけると思った」と語っていました。
あの強い印象のリフレイン(ダ・ダーダダ・・・)。一度聴くだけで脳裏に焼き付くアイコン・記号のようです。
僕は、ギター弾きでペイジに対して想い入れの強いファンであるので(小学校を卒業するまでに解散していたので後発のファン)どうしても彼の音やフレーズを意識することになります。
ギターソロに注目すると、線の細い音が聴こえます。ペイジのレス・ポールサウンドは、他のアーティストのレス・ポール・サウンドと比べると、かなりトレブリー・繊細な音作りをしていることがわかります。ペイジが音としてはテレキャスターの切れ味の良さを気に入っていたからでしょう。
映像で確認してもやはりそうです。ペイジがメインギターをテレキャスターからレス・ポールへ持ち替えたことで、バンドの音楽面・ビジュアル面にカリスマ性を与えたことは間違いありません。
また、ドキュメンタリー映画の中では「Whole Lotta Love」の中間部、あのカオスなテルミンのセクションについても興味深い証言がありました。(少年時代の僕はあのパートはあまり好きではありませんでした・・・狂熱のライブのビデオを観るまでは。。。)
ペイジは、レコード会社が勝手に曲を短く編集してシングルカットすることを極端に嫌っていました。そのため、わざとラジオでは流せないような長いノイズパートを挿入し、「これならシングルにはできないだろう」と考えたというのです。(実際はアメリカのラジオ局が勝手に編集したバージョンでオンエアし、ペイジ激怒ということもありました。僕、昔ラジオマンだったのでゴールドディスクという古い楽曲を集めた放送局用CDで実際に聴いたことがあります。)
ここから見えるのは、ペイジが単なるギタリストではなく、楽曲の届き方までを設計する「演出家」であり「編集者」であったという事実です。
キュレーター・編集者としてのジミー・ペイジ
すみません、どうしてもペイジに思い入れが強いのでペイジ語りブログになってきました・・・
さて、ZEPを語る上では避けて通れないことのひとつに盗作問題があります。
ZEPは、初期の作品で特に過去のブルースのフレーズからヒントを得たり、時には拝借することが多いことはコアなファンの方ならご存じのこと。訴訟に及んだケースもいくつかあり、何とも残念な事実です。中でもこのセカンドアルバムはその印象が強いと思います。
盗作問題を視点を変えて考える
他人のアイデアを使ったなら、なぜ制作当時にクレジットにしっかりと入れなかったのか?と思いますよね。
セカンドアルバムでの同問題のある曲としては・・・
1,「WHOLE LOTTA LOVE」:マディ・ウォーターズ「You Need Love」からの引用。訴訟で長く争われ1985年に和解し、以降クレジットにウィリー・ディクソンが入る。
2,「THE LEMON SONG」:ハウリン・ウルフの「Killing Floor」を土台に、デルタ・ブルースの伝説ロバート・ジョンソンの「Travelling Riverside Blues」の歌詞から引用。ハウリン・ウルフからの提訴を受け和解。
・・・と大きな事例を二つ揚げました。書いていても「なぜ当時にクレジットを」と感じますが、60年代、70年代はこういうアイデア拝借についての感覚が緩かったのでしょう。また、ペイジはレコード・コレクターとしての側面も持っていたので埋もれたブルーズサウンドを掘り起こすことが先人たちへの敬意だと考えていたのではないでしょうか?もともとZEPの基本コンセプトが「ブルーズを大音量で演奏する」ということでありましたし、あまり問題とはとらえていなかったのでは?と考えます。しかしながらプラントは「若気の至りで考えが追いついてなかった」という意味の謝罪のコメントも残しているのも事実。
そこでふと頭によぎったのがアンディ・ウォーホル的な編集者的・再構築術です。
ウォーホルは、マリリン・モンローやエルビス・プレスリー、キャンベルのスープ缶などをシルク・スクリーンで反復したり、何種類も色を変える手法の作品で世界に衝撃を与えた作家。既にあるものに手を加えることでアイコン化し、消費社会に溢れるものでもアートになり得るか?と問いかけました。
このすでにあるものに手を加えることで、新たな見え方、価値を与えるウォーホルの手法に、ペイジ=ZEPのブルーズ引用の楽曲制作との共通点があると考えたのです。(ポジティブに捉え直してみました。個人的な考察ですのでお許しを!)
ウォーホルの作品は彼自身がキャンバスに描いたものではなく既存の対象を使い、スタッフに指示し刷りあげ作品にしていますがれっきとした「ウォーホル作品」となっています。
対してペイジの場合もブルーズからの引用で楽曲を作りながらも、出来上がった作品は誰が聴こうとも「LED ZEPPELINの音楽」。引用しながら自己のサウンドへと進化・昇華させています。
2人の編集者的な再構築術は、素材(オリジナル)をどう見えるか?どう聴こえるか?に重点を置いた思考で作品に仕上げ世に送り出しました。
こう考えていくとサンプリングによる音楽制作も同じ意味合いとも捉えられそうです。まさかウォーホル、ペイジとサンプリング手法が重なってくるとは。。。そういえばペイジは、アメリカ版ゴジラでパフ・ダディと組んでいましたね。ヒップホップと繋がってしまいました。
まとめ
LED ZEPPELINⅡの「Whole Lotta Love」のあのリフは、アンディ・ウォーホルの「マリリン・モンロー」のように、一撃で記憶に刷りこむ「音のアイコン」であったということ。そのアイコン=記号は50年以上たった今でも鮮やかに輝き続けています。ずっと古びないサウンド。LED ZEPPELINがロック界において唯一無二の存在である理由、それは彼らの音がアートであるということではないでしょうか?
最後まで読んでくださりありがとうございました。
次はZEPⅢを書きます。では。。。